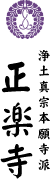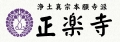東井先生は子どものころから、体はあまり丈夫ではなかったようです。
「私は、生まれつき、いわゆる腺病質体質というのであったようで、村のおばさんたちが『お寺のぼんちゃんは、お気の毒だけど、とても30歳までは生きなさらんだろう』と噂していたと聞いています」と述べられています。
次の文章は、1927(昭和2)年、兵庫県の姫路師範学校に15歳で入学されたときの思い出です。
入学した以上は、必ず何か運動部に入らなければならないということで、いくつかの運動部の門を叩かれたそうです。
* *
はじめ、サッカー部の入部検査を受けました。
山の中の、貧しく小さな小学校で育った私には、あんなボールを蹴らせてもらうのは初めてでした。
(中略)
次は、野球部でした。生まれてはじめて、バットというものを握りました。なぜ、球が当たりやすいように平らにしておかないのか、こんなツルツルした丸太ン棒を、飛んでくる球に当てるなんて、まるで奇術ではないかと思いながら、バットを振りましたが、やはり、球は当たってくれませんでした。
次は庭球部でした。ラケットを握るのも初めてでしたが、これは、球が当たるようにうまくできていると、感心しながら振りましたが、見事に空振りで、はねられてしまいました。
次は、水泳部でした。プールの波が光っているのを見ると、おそろしくなって、尻込みしている私を、水泳部の上級生が、無理やりプールに突き落としました。カナヅチが浮く道理がありません。溺れてしまった私を、上級生が大あわてにあわてて引き上げてくれました。
次は競走部でした。これは溺れるはずがありませんから、少し、安心しました。100メートル走らされましたが、ビリでした。
「チョボイチご飯」を食べて育った栄養失調の私には、人並みに走れるだけのエネルギーもなかったのでしょう。
「おまえ、なーんにもあかんのやな」と、上級生たちが、あきれ顔で申しました。
その私を、気の毒そうに見ていた上級生の1人が、「おまえ、辛抱強く粘ることはできるかい」と、尋ねてくれました。
「はい、粘ることならできると思います」と、答えましたら、
「そうか、それではマラソン部にとってやる」といってくれました。
やっと、私の落ちつくところが決まったのでした。
「よし、粘り抜いてやろう!」と、一大決心をして、入部させてもらいました。
放課後、他の部員たちと一緒に、姫路の城北練兵場をとり囲む道を一周して帰るのが、毎日の日課でした。
マラソンも、ただ粘ればよいというものではなく、毎日、私が、ビリッコを独占することになりました。
練兵場一周は五千メートルということでしたが、週1日は、市川の鉄橋まで往復、というのがありました。
これは、一万メートル だということでした。この一万メートルコースの途中に、キリスト教の女学校がありました。大勢の女学生たちが見ている前を、仲間から何百メートルもおくれて、犬に吠えられながら走るのは、鈍感な私にも、ほんとうに、つらいことでした。
(中略)
ビリッコを走りながら、毎日、考えたことは「兎と亀」の話でした。あの話では、亀は兎に勝ちました。
けれども、兎が亀をバカにして、途中で一眠りしたりするものだから、たまたま、亀が勝ったにすぎません。
いくら努力しても、亀は、どこまでいっても亀で、走力は、とても兎には及びません。
ですから、あの話は、ねうちのある亀は、つまらない兎よりは、ねうちの上では上だという話ではないかと考えました。
亀は、いくら努力しても、絶対、兎にはなれない。
しかし、日本一の亀にはなれる。
そして、日本一の亀は、つまらない兎よりも、ねうちが上だという話ではないかと考えるようになりました。
「よし、日本一のビリッコになってやろう」と、考えることで、少し勇気のようなものが湧いてくるのを感じました。
そのうちに、また、気がつきました。
「もし、ぼくがビリッコを独占しなかったら、部員の誰かが、このみじめな思いを味わわなければならない。他の部員が、このみじめな思いを味わうことなく済んでいるのは、ぼくが、ビリッコを独占しているおかげだ」ということに気がついたのです。
「ぼくも、みんなの役に立っている」という発見は、私にとって、大きなよろこびとなりました。
世の中が、にわかに、パッと明るくなった気がしました。
そして「教員になったら、ビリッコの子どもの心の解ってやれる教員になろう。とび箱のとめない子、泳げない子、勉強の解らない子どもの悲しみを解ってやれる教員になろう。『できないのは、努力が足りないからだ』などと、子どもを責める教員にはなるまい」と思わずにはおれなくなりました。