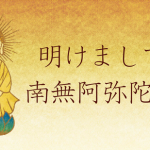私の娘は、幼い頃、九十九パーセントまでだめだといわれるような大病を何回も患いました。
全く全く不思議に、いのちを助けていただいたのですが、幼い体に何百本もの注射を打っていただいた体です。
学校に上がらせてもらうようになって、一番つらかったのは運動会でした。
みんなから何十メートルもおくれて、ドタン、ドタン、肥満の娘が走っているのを見るのは、ほんとうにつらいことでした。
私も師範学校に学んだ時、マラソン部で、四年間、毎日ビリッコを引き受けて走った男ですから、ビリのつらさは誰よりも身にみて知っているつもりですが、娘のビリを見るつらさは、自分のビリのつらさの比ではありません。
妻など「あんな姿を見せものにするなんて残酷すぎます。先生にお願いして、徒走競技だけは赦してやってもらってください」と泣いて訴えるのでした。
でも、私はそのお願いをしませんでした。
私がビリッコの中で得難いものを学ばせてもらったように、娘にも、ビリッコを背負うことによってのみ学べるものを学んで欲しかったからです。
ですから、私がビリッコの中で学んだものを何かの機会にさり気なく話して聞かせたり、「きょうのおまえのビリッコは涙がにじんで仕様がないほど立派だったぞ」と励ましてやったりすることによって、ビリッコを背負いぬく生きざまを育てようと念願しました。
娘は、戦後の物の不自由なさ中で学校生括を送りましたが、
「お父ちゃん、今度も靴の配給のくじがあたりませんでした」
「あたってほしかったな、足の指が全部出てしまっているんだからな」
「でも、わたしにあたったら人にあたらないでしょう。わたしはがまんできるから、がまんのできない人にあたった方がよかったんだと思います」
などと、配給のあたらなかった事実をぐずぐずいわないで背負って生きる生き方を見せてくれることもありました。
私の所は辺地ですから、高校は寄宿舎に入舎させました。
日曜日、寄宿舎に帰っていったと思ったら、すぐ手紙をよこしました。
「きょう、数学の答案を返していただきました。予想していたのよりよい点がついており六十点です。
おかしいなと思って調べてみると、一つ、まちがいが正答になっています。
私は黙っていようかなと思いました。だって先生にそれを言えば、六十点でもよい点ではないのに、この点から二十点も引かれてしまいます。
それは、わたしにとってほんとうにつらいことです。でも、わたしは、思いきって先生に申し出ました。
先生は、これでよいのだと強くおっしゃっていましたが、私が精しく説明すると、ほんとだね、といって四十点と訂正してくださいました。そして『正直だね』とおっしゃいました。
わたしは、バッと顔の赤くなるのを感じました。
だって、わたしは、ずいぶんこのまま黙っていようかと考えたんですもの。
でも、もうちょっとのことで、二十点どころではない汚点を、わたしの人生につけてしまうところでした。
お父さま、お母さまのおかげで、まちがいを犯さないですみました。
お父さま、お母さまも、きっと喜んでくださることと思います」
という手紙でした。
私は、娘が親譲りの頭の悪さをごまかさないで、堂々、背負おうとしてくれているのが嬉しくてなりませんでした。百点をとってくれたことより嬉しいと思いました。
自分の荷まで他人のせいにしてブツブツいう背負い方だけは育てたくないと思います。ただ、一度の自分の人生なのですから。