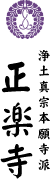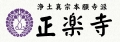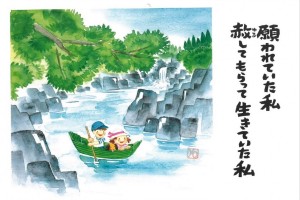
当時、私は高等二年の男子を担任していました。三学期の終りでした。理科の時間だったと思います。
「これで、高等科の理科の勉強はすべて終ったわけだが、何か質問は残っていないかい」
といったとき、ぱっと挙手したのは北村彰男という子どもでした。母一人子一人の貧しい家の子どもで、
小学校三年の時から、毎朝三時半に起きて、豊岡の町を新聞配達して廻り、帰って勉強し、それから朝食をすませて学校にやってくる子どもでした。
私が指名しますと、
「先生、あああと口をあけると、のどの奥の方にベロンと下ったぶさいくな肉片が見えてきます。あれは、一体、どういう役目をしている道具でしょうか」
というのです。
「北村君、すまんが、先生はあれの役目を知らんわい。きょう帰って調べてみるからな、明日まで答えを待ってみてくれんかい」
という以外ありませんでした。はずかしいことですが、私は教師のくせに、あののどの奥のベロベロしたものの役目を知らなかったのです。
下宿へ帰るなり、人体に関するあらゆる書物を引っ張り出して調べてみてやっとわかったのです。ものを飲み込む時、
のどの奥のところで、気管の道と食堂の道が岐れているわけですが、口からはいっていった食べ物が気管の方へいってしまったら
たいへんです。窒息してしまいます。それをそうさせないために、たべものをのみ込むときには、あのベロベロしたものが、
気管への入口を蓋してくれるわけです。そのおかげで、食物がまちがいなく胃袋の方へはいっていってくれるわけです。
それがわかったとき、私は、頭の上がらない思いにさせられました。だって、あのベロベロの役目を知らないくらいですから、
一度だってお礼を言ったことはありません。すまんなあと思ったことだってありません。すまんと思わないどころか、
「わしが生きていてやるのだ」というような驕慢さで生きていた私だったのです。そういう私のために、生まれて母親の乳を呑み
はじめたそのときから、働き通しに働いていてくれたのが、のどの奥のあのベロベロだったのです。