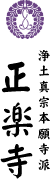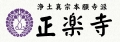一昨年、春の遠足で、私は五年生の子どもについていきました。妙見山という山の
麓の日光院という古いお寺の境内でお昼にさせてもらったのですが、子どもたちが弁当
の包みをほどいたのを見てまわりまわりながら、私は悲しい思いにとりつかれてしまいました。
あちらにもこちらにも、町のおすし屋さんで買った巻ずしを持たせてもらっている子がいるのです。
子どもたちは毎日、学校の給食をたべているのです。遠足の弁当くらい、いくら忙しくても
めんどうでも、おかあさんが心をこめてつくってやってほしいなと思いました。
間もなく、六年生の修学旅行が行われましたが、旅行の計画をみると「一食弁当持参」
ということになっていました。そこで私は、おかあさんたちに集まってもらい、おねがいしました。
「今度の修学旅行の弁当、もう巻ずしはやめにしてください。おかあさんたちが忙しいのは
よーく知っています。でも、子どもにとっては一生涯の思い出になるたいせつな修学旅行です。
いつもより早く起きてご飯をたいて、しっかり性根をいれて、ギューッと握ったおにぎり
を持たせてください。そして、忙しいのはよーく知っているつもりですが、そのおにぎりのひとつひとつに、
どんな心をこめてくださったか、それを手紙に書いてつけておいてください」
と頼んだのです。
さて、塚口の郡是の工場でお昼にさせてもらったのですが、子どもたちが弁当の包みを
ほどいてみますと、みんな大きなおにぎりです。私たちも、もちろんおにぎりです。
子どもたちのおにぎりには、おかあさんの手紙がついてます。ふだんはやんちゃをやって
仕方のない六年生の男の子が、そのおかあさんの手紙を、ジーッと涙をにじませながら
読んでいます。私の隣には森本雄二君という子がいましたが、やはり涙をにじませながら
手紙を読んでいます。もうほかのこどもたちがおにぎりにかぶりついても、
まだ一生けんめい手紙を読んでいます。森本君が読み終わった頃には、もうみんな
たべていましたが、別にあわてるでもなく、ていねいにその手紙を折りたたむと、
おまもりのようにたいせつそうに、自分の胸のポケットに納めました。
子どもたちはみんな、自分の心にふれてくるものを求めています。心と心、いのち
といのちのふれあいを、粗末にしているのが私たちではないでしょうか。