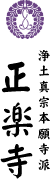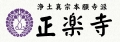親と子、夫婦がそろって無事に一日をすごすことができ、六百の子どもの上にも、二十四の教室の上にも、建物の上にも、事がなく一日が暮れたということ、それがどんなにただごとでないことであるかを、痛感させてもらうこの頃です。
私が中学校の校長を勤めさせてもらっていた頃のお正月でした。
例年のように「おめでとうございます」の会を開きました。
そのとき、私は、
「大黒さまは、いつ見ても背中に大きな袋をかついでいらっしゃる。
そして、いつ見てもニコニコしていらっしゃる。
生徒の皆さん、あの袋の中には、いったい、何がはいっているのだろうか。
いつもニコニコしていらっしゃるところをみると、だいぶ、いいものがはいっているにちがいないのだが、何がはいっているのだろうか?」
と、質問しました。
一斉に手があがりました。
一人の生徒を指名しますと、
「きっと、お金がたくさんはいっているのだと思います。
だからあんなにうれしそうな顔をしていらっしゃるのだと思います」
「ほかの考えの人はいませんか?」
と、尋ねてみましたが、一人も手をあげる生徒はいませんでした。
みんな、一人残らず、お金がはいっていると信じているようでした。
「そうかもしれないね。あんな大きな袋にお金を入れたらずいぶんたくさんはいだろうな。
だからあんなにふれしそうな顔をしていらっしゃるのかもしれないね。
だけど、ずいぶん重いだろうな。
かついだときは嬉しかったろうが、その重みがだんだん肩にくいこんできたら、しかめっつらになってくるのではないだろうか。
だのに大黒さまは、いつもニコニコしていらっしゃる。
ひょっとすると、お金ではないのかもしれないよ。
お金でないとすると何だろうか?」
と、問いをまた生徒に返しました。
いつまで待っても手があがりません。
その中、生徒の一人が、
「校長先生は何がはいっているとお考えですか?」
と、逆襲してきました。
「さて、わたしにも確かなことはわからないが、ひょっとすると、あの中には『よろこび』がはいっているのではないだろうか。
だから、あんなにうれしそうなお顔をしていらっしゃるのではないだろうか」
と、答えました。
そして、
「わたしたちは、みんな、それぞれ、背中に一つずつ袋をいただいているのではないだろうか。
そして、しあわせな人というのは、背中にたくさん『よろこび』を貯えている人のこと、不幸な人というのは、背中の袋に、不平・不満・愚痴を入れて背負っている人といえるのではないだろうか。
お互いに、きょう、こうして新しい年を迎えたわけだが、何とか、今年という年を、光いっぱいの年にするために、『よろこび』をいっぱい貯える年にしようじゃないか。
ところが、わたしは町の大売出しの福引き券をひいても、マッチの小箱くらいしかあたったことはない。
わたしはどうやらそういう宿命を背負っているらしい。
だから『大きいよろこび』とは無縁らしい。
そこで、考えた。
みんなが拾い忘れている『小さいよろこび』をたくさん貯えることにした」
と、宣言したことでした。
私は、小さいノートを持ち歩いておりまして、よろこびが見つかると、それを書きとめておくように努めているのですが、うっかりしえちると見すごしてしまいそうな小さく見えるよろこびが、みんな、すばらしい大きいしあわせにつながっていることに気づかせていただくのです。
若い頃にはうっかりしていたことの中に、こんな大切なしあわせがあったということを驚くとともに、こういうしあわせにであわせていただけるのは、年とったおかげさまかな、ありがとうと、よろこばせていただくのです。
きゅうりの漬物が 満点の味をひっさげて
わたしのために
かぼちゃも 茄子も 長豆も
それぞれが それぞれの最高の味をひっさげて
わたしのために
わたしのたるんだ胃袋に 目を覚まさせるために
さんしょも 食卓に 梅ぼしもその横に
もったいなすぎる もったいなすぎる
せめて わたしも きゅうりの漬物のひときれにでもなって
どなたかの胸に よろこびの灯をともしたい
さんしょの一粒にでもなって
生きがいを失っている人に
生きがいの 目を覚まさせてあげたい
思いあがるなと
叱られてしまいそうな気もするが……
東井先生は子どものころから、体はあまり丈夫ではなかったようです。
「私は、生まれつき、いわゆる腺病質体質というのであったようで、村のおばさんたちが『お寺のぼんちゃんは、お気の毒だけど、とても30歳までは生きなさらんだろう』と噂していたと聞いています」と述べられています。
次の文章は、1927(昭和2)年、兵庫県の姫路師範学校に15歳で入学されたときの思い出です。
入学した以上は、必ず何か運動部に入らなければならないということで、いくつかの運動部の門を叩かれたそうです。
* *
はじめ、サッカー部の入部検査を受けました。
山の中の、貧しく小さな小学校で育った私には、あんなボールを蹴らせてもらうのは初めてでした。
(中略)
次は、野球部でした。生まれてはじめて、バットというものを握りました。なぜ、球が当たりやすいように平らにしておかないのか、こんなツルツルした丸太ン棒を、飛んでくる球に当てるなんて、まるで奇術ではないかと思いながら、バットを振りましたが、やはり、球は当たってくれませんでした。
次は庭球部でした。ラケットを握るのも初めてでしたが、これは、球が当たるようにうまくできていると、感心しながら振りましたが、見事に空振りで、はねられてしまいました。
次は、水泳部でした。プールの波が光っているのを見ると、おそろしくなって、尻込みしている私を、水泳部の上級生が、無理やりプールに突き落としました。カナヅチが浮く道理がありません。溺れてしまった私を、上級生が大あわてにあわてて引き上げてくれました。
次は競走部でした。これは溺れるはずがありませんから、少し、安心しました。100メートル走らされましたが、ビリでした。
「チョボイチご飯」を食べて育った栄養失調の私には、人並みに走れるだけのエネルギーもなかったのでしょう。
「おまえ、なーんにもあかんのやな」と、上級生たちが、あきれ顔で申しました。
その私を、気の毒そうに見ていた上級生の1人が、「おまえ、辛抱強く粘ることはできるかい」と、尋ねてくれました。
「はい、粘ることならできると思います」と、答えましたら、
「そうか、それではマラソン部にとってやる」といってくれました。
やっと、私の落ちつくところが決まったのでした。
「よし、粘り抜いてやろう!」と、一大決心をして、入部させてもらいました。
放課後、他の部員たちと一緒に、姫路の城北練兵場をとり囲む道を一周して帰るのが、毎日の日課でした。
マラソンも、ただ粘ればよいというものではなく、毎日、私が、ビリッコを独占することになりました。
練兵場一周は五千メートルということでしたが、週1日は、市川の鉄橋まで往復、というのがありました。
これは、一万メートル だということでした。この一万メートルコースの途中に、キリスト教の女学校がありました。大勢の女学生たちが見ている前を、仲間から何百メートルもおくれて、犬に吠えられながら走るのは、鈍感な私にも、ほんとうに、つらいことでした。
(中略)
ビリッコを走りながら、毎日、考えたことは「兎と亀」の話でした。あの話では、亀は兎に勝ちました。
けれども、兎が亀をバカにして、途中で一眠りしたりするものだから、たまたま、亀が勝ったにすぎません。
いくら努力しても、亀は、どこまでいっても亀で、走力は、とても兎には及びません。
ですから、あの話は、ねうちのある亀は、つまらない兎よりは、ねうちの上では上だという話ではないかと考えました。
亀は、いくら努力しても、絶対、兎にはなれない。
しかし、日本一の亀にはなれる。
そして、日本一の亀は、つまらない兎よりも、ねうちが上だという話ではないかと考えるようになりました。
「よし、日本一のビリッコになってやろう」と、考えることで、少し勇気のようなものが湧いてくるのを感じました。
そのうちに、また、気がつきました。
「もし、ぼくがビリッコを独占しなかったら、部員の誰かが、このみじめな思いを味わわなければならない。他の部員が、このみじめな思いを味わうことなく済んでいるのは、ぼくが、ビリッコを独占しているおかげだ」ということに気がついたのです。
「ぼくも、みんなの役に立っている」という発見は、私にとって、大きなよろこびとなりました。
世の中が、にわかに、パッと明るくなった気がしました。
そして「教員になったら、ビリッコの子どもの心の解ってやれる教員になろう。とび箱のとめない子、泳げない子、勉強の解らない子どもの悲しみを解ってやれる教員になろう。『できないのは、努力が足りないからだ』などと、子どもを責める教員にはなるまい」と思わずにはおれなくなりました。
もう、何年くらい前になるでしょうか。
毎日新聞社会部がまとめた『幸福ってなんだろう』(エール出版刊)という本が出版されました。
その本の「はしがき」に書かれた文章を、私は今も忘れることができません。
ご縁のある多くの皆さんにたびたびご紹介しているうちに、いつの間にか、私は、その文章を暗記してしまいました。
ご紹介しましょう。
昨年十二月。私の最愛の人が四十八年の生涯を終わって、永遠の眠りについた。
乳ガン手術後の転移ガンである。
その年の三月から脊髄が侵されて下半身がマヒし、大阪の自宅で寝たきりであった。
医者は「あと半年のいのち」と宣告した。
そのころ私は勤務地の福岡にいた。
大阪と福岡。
離ればなれのふたりは、毎晩、短い電話をかけあった。
彼女の枕元の電話機が「夫婦の心」を知っていよう。
彼女は自分の病気が何であるかをうすうす悟っていた。
死ぬ一カ月前。
真夜中に電話をかけてきた。
いつもの澄んだ声である。
「おきていらっしゃる?」
「うん」
「夜中に電話をかけてごめんなさい。私眠れなかったの」
「痛むか」
「痛むの。でも…」
しばらく声がとぎれた。
「私の一生は、本当に幸福な一生でしたワ」
泣いているようである。
受話器を持つ私の手はふるえた。
妻よ。
感謝すべきは、この私ではなかったか。
二十三年間、ずいぶんと苦労もかけたのに、彼女は私と子どもたちのために、よくつくしてくれた。
明るい家庭の太陽であったのに。
ーーという文章です。
奥さんには、ご自分の病気が何であるかわかっていらっしゃるのです。
末期癌の痛みの中で、いよいよ、自分の最期の日が近づいていることを、お感じになっているのです。
如来さまは、きっと奥さんのその絶望的なお心の中におはいりになって、絶望の淵から、奥さんを引き戻そうとなさって、光を放って、ご主人の大きな愛情に包まれて歩まれた、今までの人生の輝きをお見せになったのでしょう。
今までの人生の輝きをご覧になると、奥さんは、その感動をひとり占めしておくこがおできにならず、真夜中、電話で、その感動をお伝えになったのでしょう。
それをご縁に、「妻よ、感謝すべきは、この私ではなかったか」と、この奥さんに支えられてきた人生の輝きに、感動のあまり、受話器をおもちになる手がふるえたのでしょう。
このご夫婦が、仏法にご縁のある方であったかどうか、私にはわかりません。
でも、そんなことにかかわりなく、如来さまは一切衆生のために、はたらきつづけていてくださるのでしょう。