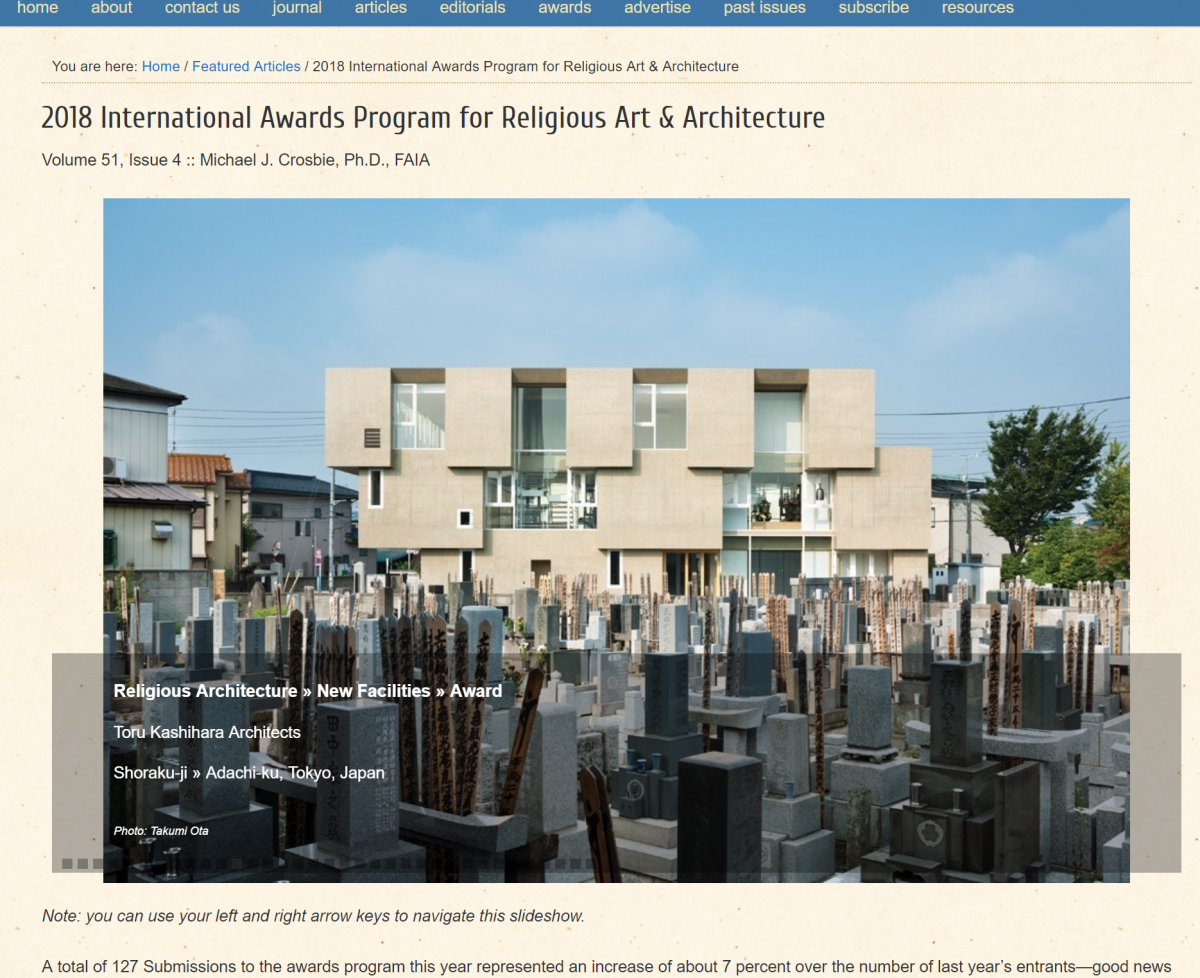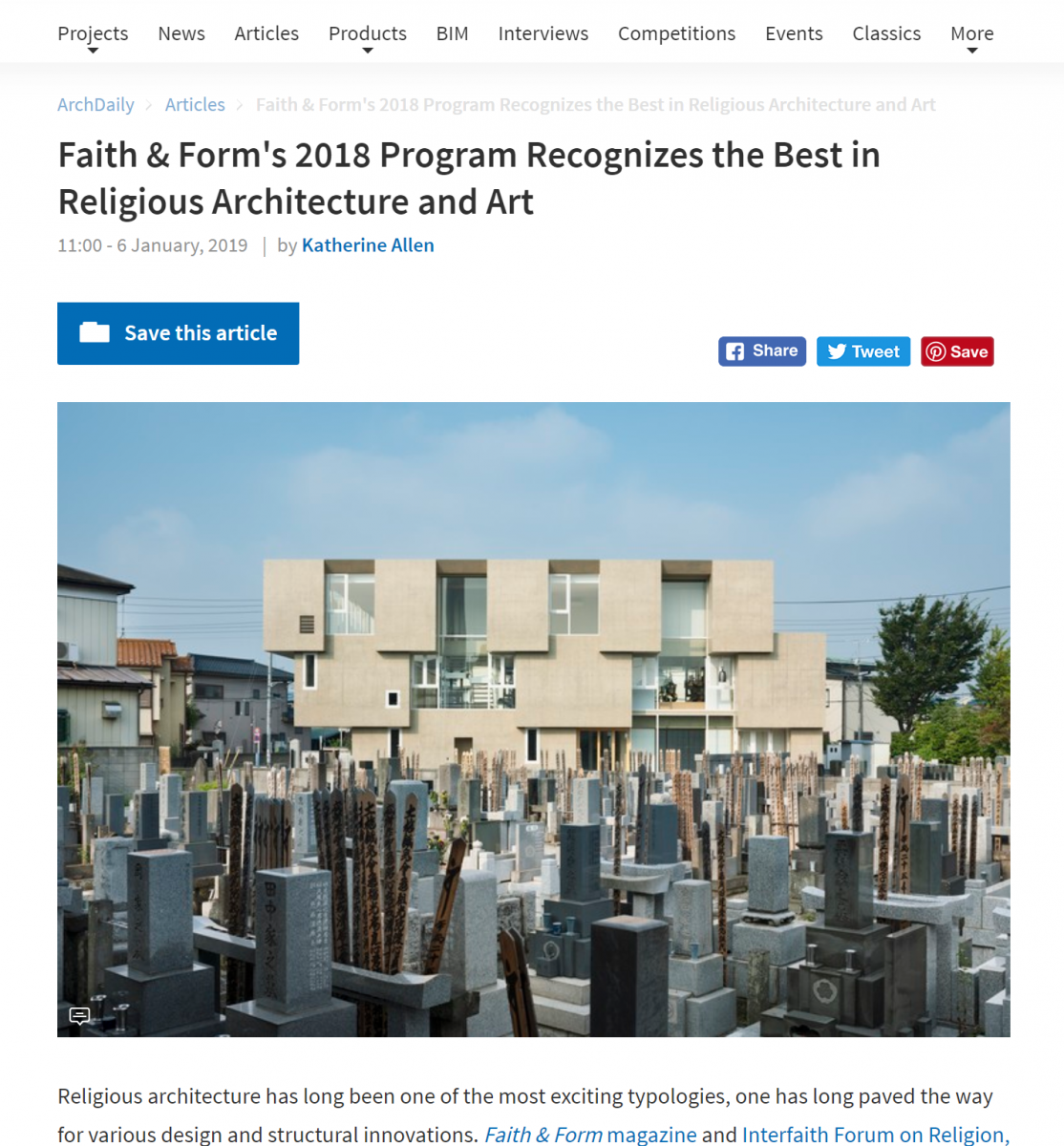隣の町のお寺の門前の掲示板に、
「目をあけて眠っている人の目を覚ますのは、なかなかむずかしい」
と書いてありました。
「目をあけて眠っている人」
というのは私のことではないかと思うのといっしょに、悪性腫瘍のため亡くなられた
若き医師、井村和清先生が、飛鳥ちゃんというお子さんと、まだ奥さまのお腹の
中にいらっしゃるお子さんのために書き遺された『飛鳥へ、そしてまだ見ぬ子へ』(祥伝社刊)
というご本のことを思い出しました。
その中に「あたりまえ」という、井村先生が亡くなられる二十日前に書かれた詩があります。
あたりまえ
あたりまえ
こんなすばらしことを、みんなはなぜよろこばないのでしょう
あたりまえであることを
お父さんがいる
お母さんがいる
手が二本あって、足が二本ある
行きたいところへ自分で歩いてゆける
手をのばせばなんでもとれる
音がきこえて声がでる
こんなしあわせはあるでしょうか
しかし、だれもそれをよろこばない
あたりまえだ、と笑ってすます
食事がたべられる
夜になるとちゃんと眠れ、そしてまた朝がくる
空気を胸いっぱいすえる
笑える、泣ける、叫ぶこともできる
走りまわれる
みんなあたりまえのこと
こんなすばらしいことを、みんなは決してよろこばない
そのありがたさを知っているのは、それを失くした人たちだけ
なぜでしょう あたりまえ
お寺の前で、私は、井村先生の詩と共に、今は亡き塩尻公明先生のおことばを
思い出しました。
「人間は、無くてもがまんできることの中に幸せを追い求め、それがなくては
しあわせなど成り立ちようのない大切なことを粗末に考えているようだ。例えば、
子どもが優等生で、有名中学に入学するというようなことの中にしあわせを追い求め
るあまり、子どもが健康でいてくれるというような、それなしにはしあわせなど成り
立ちようのない大切なことを、粗末に考えているのではないか」
という意味のおことばでした。
「それなくしては、しあわせなど成り立ちようのない大切なこと」「あたりまえ」
のすばらしさの見えない人、そういう人を「目をあけて眠っている人」というのだ
と思いました。